観光・体験
Sightseeing & Activity

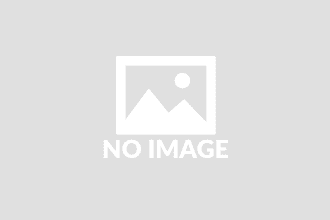
ここは、神功(じんぐう)皇后の新羅遠征で功績のあった武内宿彌(たけのうちのすくね)が、香椎在陣中に居住したと伝えられている。宿彌は300歳までも生きたという伝説の人である。
近くの不老水は宿彌の長寿にちなんだもので、以前は香椎宮の綾杉(あやすぎ)の木と共に皇室に献上されていた。不老水は長寿の神秘を物語るように、汲めどもつきぬ水を湧かせている。

大乗寺は法皇山宝珠院と号して、昔は奈良西大寺の末寺で律宗に属し、亀山上皇の勅願寺でありましたが、のち浄土宗に転じ、更に真言宗に改宗、大正9年(1920)長宮寺と合併して、中央区大手門一丁目に移り戦災で焼失しました。 この寺跡に亀山上皇が元寇の際、西大寺の叡尊(えいそん)に命じて、博多において敵国降伏の祈願を行わせた勅願石や、県指定文化財の地蔵菩薩板碑、蒙古碇石があります。

津屋崎漁港から中川までの広い砂浜。遠浅の美しいビーチで、海水浴やボートによる釣り(キス・アジ等)ができる。穏やかな波で昔から人気がある海水浴場。海の家が充実している。

緑豊かな自然を活用して、子供からお年寄りまでオールシーズン気軽に楽しむことができる公園。噴水広場、和風庭園、多目的広場、野球場、弓道場、アーチェリー場、ゲートボール場、テニスコートなどを整備している。

カシ、シイ、ムクなどの木々が重なり合って壮厳な美しさをかもし出す自然林。
この中にある樹齢900年のナギの古木5本は、行基のお手植えともいわれる。県指定の天然記念物。

墳長75m以上、高さ8mの前方後円墳で、福岡市の指定史跡。古墳時代初期に築かれたものとされている。墳丘は地山整形と盛土からなり、周囲には鍵穴形に周溝がめぐらされている。内部主体は後円部の中央に2基あり、第1主体は未調査、第2主体は長さ2.3mの割竹形木棺の直葬で、三角縁神獣鏡と玉類が出土した。福岡平野の首長墓の系譜では最古に属するものとされている。

平家落人の里として伝説の残る唐原の里。
ここの林道から谷川沿いに小道を登ると見えてくるのが千寿院の滝。
高さ約20mで白い水しぶきとなって流れ落ちる様子は見事。夏場でも涼しく、観光客で賑わう。

2011年に創立百周年を迎えた九州大学に付設している総合博物館。
研究や教育の過程で収集されたり用いられたりした膨大な学術資料や教育資産を管理。
そのごく一部の実物を、1930(昭和5)年に竣工された歴史的建物の3階にある常設展示室で見ることが出来る。
公開講演会や企画展示、子ども向けのワークショップなどもしばしば開催。特に、年に数回開催される、収蔵展示室の一般公開や、古い施設を使った...

若八幡宮神社内にある前方後円墳。福岡市指定の史跡で、4世紀後半の築造と考えられている。墳長47m、後円部三段、前方部二段の築成で、墳丘には葺石を施し、埋葬主体部は長さ2.75m、幅1.2mの舟形木棺で、後円部中心に掘られた径13m前後の円形墓壙の中に古墳長軸と直交して埋置。棺内外には三角縁神獣鏡、玉類、鉄製武器類、鉄製短甲などを副葬している。

焼かないで固まる「つちだま」を使い,植木鉢やガーデニングオブジェを作っています。
ミニガーデン用の小さなおうち,水槽用のオブジェ,かわいいペットの壁掛けなど,楽しんで作ることができます。

市内随一の大社で、古くから地域住民に親しまれています。 創立は史料の焼失などで明らかではありませんが、残っている棟札には明応2年(1493年)との記載があり、歴史の古さを物語っています。 また、境内にある大楠のこぶをよく見るとあの有名な妖精「ムーミン」そっくりだということが発見されました。この不思議な偶然は大反響を呼び、今では全国からファンが見学に訪れる名所です。

臨済宗大徳寺派の寺で、山号は龍起山。大覚禅師(蘭渓道隆)と鎌倉幕府五代執権・北条時頼を壇越として、建長元年(1249)に創建。延文5年(1360)には朝廷の勅願寺となり、これに関する文書が他の21点の中世文書とともに残されている。曲彖(椅子)に座った禅師が描かれている『絹本着色大覚禅師像』は、縦112.8cm、横59.69cmで、国の重要文化財に指定されている。

能許(のこ)という地名が文献に初めて出た歌で、荒津から出航した遣新羅使が能許の泊(現在の唐泊) で風待ちをしている時の気持ちが詠まれています。風吹けば 沖つ白波 恐みと 能許の泊まりに あまた夜そ寝る(「万葉集」3673)

曹洞宗の寺で明治の初め頃まで神宮寺と呼ばれていました。境内には地元出身の洋画家多々羅義雄(たたら よしお)の歌碑や、戦後すぐに遭難し28人の犠牲者を出した能古渡海船の慰霊碑、二八観音などがあります。

幅約20m、長さ1kmに渡って続く鳴き砂の海岸。
音の元となる石英の含有率が高く、純度の高い砂であることから、砂の上を歩くとキュッキュッと不思議な音を聞くことができる。

