観光・体験
Sightseeing & Activity


博多の方から来ると太宰府市に入ってまもなく道路や線路を横切って木立に覆われた丘が続く。それが664年、唐と新羅の攻撃に備えて築かれた防衛施設水城(みずき)である。その規模は全長1.2km、基底部の幅80m、高さ10mを超え、すべて人の手で築いた人工の土塁(土の堤防)である。そして名のとおり海側(博多側)に幅60m、深さ4mの堀を造り、水を貯えた。春日市、大野城市にも小規模な水城が残っている。

花乱の滝は、落下する滝のしぶきが、花びらが乱舞するように美しいこと、または、花欄という修験者がいて、この滝にうたれて修行したということから、「花欄の滝」と呼ばれるようになったといわれています。
滝の高さは、約15m、幅3.5mあって、滝つぼが浅く、今でも滝にうたれて修行する人の姿が見られます。

能古島の産土神(うぶすながみ:生まれた土地の守り神)で、祭神は住吉大神(すみよしのおおかみ)・神功皇后(じんぐうこうごう)・志賀明神(しかみょうじん)などです。能古島という地名には、「神功皇后が住吉の神霊を残した島なので残島(のこのしま)になった」といういわれがあり、この神霊をとどめたのが白鬚神社だといわれています。毎年10月9日に行われる「おくんち」は、福岡市の無形文化財に指定されています。

2011年に創立百周年を迎えた九州大学に付設している総合博物館。
研究や教育の過程で収集されたり用いられたりした膨大な学術資料や教育資産を管理。
そのごく一部の実物を、1930(昭和5)年に竣工された歴史的建物の3階にある常設展示室で見ることが出来る。
公開講演会や企画展示、子ども向けのワークショップなどもしばしば開催。特に、年に数回開催される、収蔵展示室の一般公開や、古い施設を使った...

博多港引き揚げ記念碑として平成8年に建てられた、巨大なモニュメント。「敗戦直後の失意とその後湧き興ってきた生への希望を永遠に記念するモニュメント」として、豊福知徳により製作された。博多港は戦後直後、国内最大級の引揚援護港として、中国東北部や朝鮮半島より約139万人もの人々がこの地に、また、在日の朝鮮人・中国人など約50万人の人々がここから故郷へと帰っていった。戦争の悲惨な体験を二度と繰り返さ...

祭神は大己貴命など9神を祀る神社で、由緒は不詳。村内数神社の祭神を大正時代に村社の八坂神社に合祀したもの。7月14・15日の祇園祭では、獅子舞や祇園囃子(共に福岡市指定無形民俗文化財)が上演される。

続風土記拾遺にその由来が記されている日吉神社の境内と、それに隣接する那珂川の中洲全体が中ノ島公園。県天然記念物のオガタマノキなど大木が茂る中、夏はひんやりとした風が吹き利用客で賑わいます。公園内には生産物直売所もあります。

全国屈指のラドンを含む天然温泉。ラドンが療養泉基準の7倍も含まれており、高血圧症、動脈硬化症、痛風、神経痛などさまざまな効能が期待できる。また、流水浴プールや地元の旬の幸を使った食事なども楽しめる。

福岡のオアシス・大濠公園南側エリアに、八女茶をテーマとした2階建て和モダン建築の新しい施設「大濠テラス 八女茶と日本庭園と。」がニューオープン!
1階は幅の広い大きなテラス窓一面、開放感のあるナチュラルなカフェ空間です。八女茶を中心に福岡県各地域から届けられる旬な具材を厳選し、様々なメニューを楽しめるカフェもあります。レンタル着物店も併設していますので、レンタル着物を着て日本庭園や大濠...
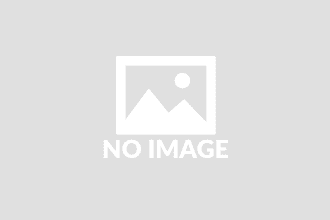
伝説では伊邪那岐(いざなぎ)の神の「みそぎ祓(ばらい)」をしたところで天照大神、志賀三神、住吉三神が出現したという由緒の地とされている。享保10年(1725)6代藩主黒田継高(つぐたか)が社殿を建立し、伊勢神宮の古例にならい、20年ごとに新旧両殿交互に改築遷座が行われていた。神功(じんぐう)皇后の休憩安産石の由緒により、安産祈願またけいれんの病に霊験があるとされている。
附近に皇后の朝鮮出兵...

貝塚駅の南南東約300m、JR鹿児島本線を挟み、東西にある元寇防塁。箱崎地区は薩摩藩が分担して防塁を築いたという記録があり、現在は一部土塁状の高まりが残っている。平成5年に試掘調査を行った際は、防塁構築石材が出土した。東側の多々良川河口には乱杭を打ったといわれている。線路西側の地蔵松原公園に説明板が建っている。

江戸時代中期のものといわれるが、九州では最も古いワラ葺きの民家。伝教大師(最澄)が中国から帰国した折りに寄宿し、世話になったお礼として「横大路」の性と「毘沙門天の像」「法理の火」「岩井の水」を贈られ、「法理の火」を千年以上守り続けていることから「千年家」と呼ばれている。また、毘沙門天の像は高さ30センチほどの高さで最澄が手彫りしたと言われ、毎年4月13日の「御開帳祭」の日だけ見ることができる...

観光客にも市民にも人気のショッピングモール、キャナルシティ博多。建物自体ユニークなモールですが、それに負けないインパクトあるアート作品が設置されています。
こちらは180台ものブラウン管テレビを使って、制作されたビデオアート作品です。作者は韓国に生まれ、日本、ドイツ、アメリカでも活躍し、「ビデオアートという芸術ジャンルを確立した世界的アーティスト」として知られる有名な現代美術家で、設置当時、...

中国の歴史書「魏志倭人伝」に記された古代王国「伊都国」をメインテーマとし、市内の遺跡から出土した数多くの貴重な文化財や歴史資料を収蔵・展示している。中でも、世界最大の銅鏡「内行花文鏡」をはじめとする国宝「平原遺跡出土品」は必見。館内には、旧石器時代から現代まで学べる常設展示室や、広大な糸島平野を見渡せる展望スペース、文化財を分かりやすく紹介する映像スペースなどがある。



