観光・体験
Sightseeing & Activity


昭和3年11月、京都御所で行われた昭和天皇の即位式で、主基殿に供えられた新米が脇山の石津新一郎が所有したこの斉田より献上された。
全国から選ばれ、古式により田植えから収穫仕上げまで、村(当時の脇山村)を挙げての大行事であった。
この斉田から白米3石(450キログラム)が献上された。

地元福岡では熱狂的な支持を得るサッカークラブ。名前はスペイン語の「クマンバチ」を意味する「アビスバ」から由来している。ハチのチームワークやスピーディな動きをなぞらえたものだ。そのためマスコットキャラクターもクマンバチを現している。地域に根ざしたスポーツクラブとして福岡市民に支持され、スポーツを通じた子供の育成など、豊かなスポーツ文化の創造に貢献している。

志賀神社境内にあり、拝殿の左前方に大枝を広げているクスの木。2本のクスの幹とナノミの幹が合体しためずらしい巨木で、根回り9.2m、樹高22.6m、樹齢は約600年といわれている。

旧早良郡飯盛・吉武・四箇・金武・田村・羽根戸・野方からなる、七ヵ村の惣社飯盛神社の神宮寺真教院の跡地に建つ。鎌倉時代には奈良西大寺の末寺であり、この地方の真言律宗の中心として栄えた。堂内には元弘3年(1333)仏師堪幸作の文殊菩薩騎獅像(市指定文化財)が安置されている。堂内に湧く『智恵の水』には受験へのご利益があるとか。

町立としては九州で初めて、また全国的にもまだまだ町立資料館が珍しかった時期に開館した先駆的な資料館。貴重な考古資料や戦前の生活用具、昭和のおもちゃまで、暮らしの歩みを語るモノを多数収蔵している。

天正15年(1587)千利休は、この燈籠堂前で、博多の豪商神屋宗湛(かみやそうたん)、島井宗室(しまいそうしつ)らと共に、九州平定のため箱崎に在陣中の豊臣秀吉を招き、たびたび茶会を催した
。このゆかりの堂は、当時筥崎宮境内にあったが、明治維新での神仏分離により、恵光院(えこういん)に移されたものである。

津屋崎漁港から中川までの広い砂浜。遠浅の美しいビーチで、海水浴やボートによる釣り(キス・アジ等)ができる。穏やかな波で昔から人気がある海水浴場。海の家が充実している。

近年の発掘調査で新たに発見された防塁で,博多の元寇防塁と推定されています。展示室があり,見学することができます。
※問合先:福岡市経済観光文化局文化財活用課 092-711-4666
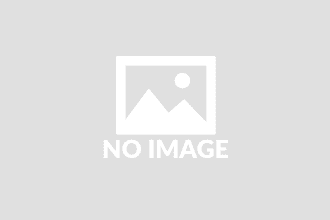
ここは、神功(じんぐう)皇后の新羅遠征で功績のあった武内宿彌(たけのうちのすくね)が、香椎在陣中に居住したと伝えられている。宿彌は300歳までも生きたという伝説の人である。
近くの不老水は宿彌の長寿にちなんだもので、以前は香椎宮の綾杉(あやすぎ)の木と共に皇室に献上されていた。不老水は長寿の神秘を物語るように、汲めどもつきぬ水を湧かせている。

多数の効能を持つ漢方励明薬湯をはじめ、露天風呂やジェットバス、サウナなどのお風呂が楽しめます。露天風呂では季節ごとに「バラ風呂」「菖蒲風呂」「みかん風呂」などのイベント湯も行っています。また、お風呂の間に休憩できる仮眠室や産直コーナーを設けたラウンジなど、ゆっくりと過ごすことができる空間になっています。

ももちのシンボル・福岡タワーの膝下にある、赤く鮮やかで力強いフォルムの印象的な大きなモニュメント。すぐそばには海があり、またその作品名から、博多湾に向かって大きく手を広げているのかなと推測したりもできますが、真相はいかに?
作者は高名な彫刻家であり、もともとは京焼窯元清水家七代目当主であった陶芸家です。器のように、力強いなかにも空気を含むような柔らかさも持ち合わせているこの作品は、1996...

今泉公園に隣接した処に、歌人大隈言道が天保7年(1836)39歳のときから住んでいた旧居「ささのや」があった。言道は二川相近(ふたがわすけちか)について和歌を、日田(大分県)の広瀬淡窓(ひろせたんそう)に漢学を学び、大阪に出て歌人らと交流するなど歌道に精進、明治元年71歳で亡くなった。墓は香正寺にある。

JR博多駅にほど近い場所にある比恵公園。中央に、高さ4メートルの大きな掌のモニュメントがそびえ立っています。山梨県出身、福岡市在住の作者は、数多くのパブリックアート作品を手掛け、また、障がい者アートのプロデュース活動も行っている彫刻家。
この作品はアジアの玄関口、福岡での出会いや別れが表されているそうです。行き交う人の時間帯、向かう方向によって感じ方が違い、「ハロー」にも見えれば「グッバイ」...

知恵の象徴として人々に親しまれているフクロウ。知恵の宝庫である福岡市総合図書館で、そんなフクロウの彫刻を見ることができます。作者は、愛知県瀬戸市出身の彫刻家。この作品では、未来に向かって夢と希望に満ちた子どものフクロウと、それを温かく見守り育てる親フクロウの姿が表されているそうです。

日本書紀によると小山田の斎宮は神功皇后の斎宮とかかれ、西暦200年、神功皇后が政務を執られたといわれる聖母屋敷の一角に立てられたとされています。社叢(しゃそう)にはブナ科スダジイとイチイガシなどが群生しており、県の天然記念物に指定されています。イチイガシの大きなものは樹齢千年以上を経ていて、胸高周囲約4メートル、高さ30メートルもあります。


