観光・体験
Sightseeing & Activity

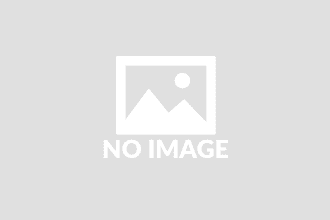
ここは、神功(じんぐう)皇后の新羅遠征で功績のあった武内宿彌(たけのうちのすくね)が、香椎在陣中に居住したと伝えられている。宿彌は300歳までも生きたという伝説の人である。
近くの不老水は宿彌の長寿にちなんだもので、以前は香椎宮の綾杉(あやすぎ)の木と共に皇室に献上されていた。不老水は長寿の神秘を物語るように、汲めどもつきぬ水を湧かせている。

毎年、5月下旬から6月上旬にかけて、ほたるの乱舞が観られる名所です。
「ほたる館」では、ほたるの生態学習ができます。
梅の森、桜の森、じゃぶじゃぶ池、風の谷、こもれびの道、銅山跡広場があり、自然体験やレクリエーション活動の場として親しまれています。野鳥のバードウォッチングも楽しめます。

交通の便が良く、町の中心に位置する文化施設として、生涯学習の“場”を開き『ゆとりある生活空間都市かすや』を創造し、必要な資料や情報を提供することを目的としています。歴史資料館には、復元作業室の公開や、地域の考古遺物や民族資料の紹介をおこなっています。
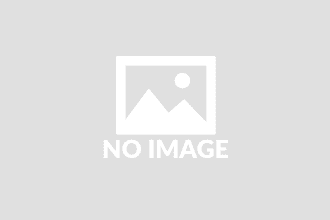
伝説では伊邪那岐(いざなぎ)の神の「みそぎ祓(ばらい)」をしたところで天照大神、志賀三神、住吉三神が出現したという由緒の地とされている。享保10年(1725)6代藩主黒田継高(つぐたか)が社殿を建立し、伊勢神宮の古例にならい、20年ごとに新旧両殿交互に改築遷座が行われていた。神功(じんぐう)皇后の休憩安産石の由緒により、安産祈願またけいれんの病に霊験があるとされている。
附近に皇后の朝鮮出兵...

曹洞宗補陀山興宗寺の境内、右側丘陵の半腹に南向きに位置している円墳。墳丘の推定直径は約20mで、石室は複室構造の横穴式。古墳時代後期のものとされている。石室内の奥の間の正面には阿弥陀、左右には観音、勢至両菩薩が彫られている。作者・製作時期は不明だが、その形態から穴観音と呼ばれて信仰されている。

田島の辺津宮、大島の中津宮、海の正倉院沖ノ島の沖津宮の三宮を総称して宗像大社という。
全国6000余りの宗像大社の総社で、古来から海陸交通 の守り神として信仰されてきた。
沖ノ島で発掘された8万点の国宝は、大社が所有し、境内の中にある神宝館に展示されている。

真言宗御室派で、山号は登志山。怡土荘の中原氏の娘の発願で、安元元年(1175)に栄西を招いて創建された。怡土荘は山城仁和寺領で、仁和寺ゆかりの僧である栄西は今津湾を臨むこの寺に10余年間滞留し、宋船のもたらす経典の入手に努めた。栄西自筆の盂蘭盆縁起は国宝に指定されている。銭弘俶八万四千塔や、孔雀文沈金経箱は、国指定の重要文化財。

津屋崎千軒の西に位置する高さ114mの大峰山の山頂周辺の海と山に囲まれた景勝地。
山頂には、日本海海紀念碑があり、街並みや水平線を一望できる。遊歩道やキャンプ場、東郷神社などがある。春は桜が美しい。
空気が澄んでいるときは、沖ノ島が見える。

福津市の水がめである久末ダム周辺を公園として整備したもので、野球場、テニスコート、多目的広場があります。ダム周辺は散策の場として四季折々の自然とふれあうことができます。また、久末ダムは、バードウォッチングが楽しめ、冬場は鴨類などの水鳥も飛来します。

明治32年、博多誓文晴(払)の創始者漬物屋 八尋利兵衛(やひろりへい)が住吉から中洲付近まで開発し、遊園地「向島」を開園した。
その開園記念に建設された灯籠で、昭和29年清流(せいりゅう)公園内に移された。灯籠には商屋の家号が刻まれていて、当時の博多経済界を知る上で貴重な民俗資料である。

墳長85m、高さ8mの前方後円墳。高祖山から北にのびる丘陵端にある。墳丘斜面には葺石があり、墳頂部と段テラスの三段に円筒埴輪がめぐっていて、石室内からは鏡や匂玉、鉄刀などの副葬品が出土した。5世紀前半の築造で、今宿平野のみならず糸島平野全体を掌握した首長の墓と考えられている。国指定史跡。






