観光・体験
Sightseeing & Activity


日本の世界遺産国内推薦となった国道495号線を挟んだ5~6世紀の古墳群。
宗像君(むなかたのきみ)一族の墓と考えられ、学術的にも重要なもの。
前方後円墳5基を含む41基が畑の中に分布しており、比較的見学しやすい。
調査された古墳からは、鉄のよろいや鉄を作る道具、飾りがつけられた土器などの史料が出土した。

旧唐津街道の宿駅、筑前21宿のひとつ。
都落ちした三条実美らが投宿し、本陣からの眺望を絶賛したと言われる。現在でも白壁、格子造りの家並みが続き、辻井戸なども残っており、江戸時代の面 影を今に伝えている。

東を除く三方を海に囲まれた戦国時代の平山城。東西840m、南北280~400mの規模で、北に本丸、南に二の丸、三の丸を配し、海水を引き込んだ堀割と空堀で周囲を防御していた。天文年間(1532~1555)に立花城主・立花鑑載が支城として築造したとされ、天正15年(1587)に小早川隆景が大改修を行なった。初代福岡藩主・黒田長政も初めはここを居城としたが、城下町の発展に不便な土地であることから、...

祭神は素盞鳴命、櫛稲田姫命、大己貴命。明治年間(1868~1912)に村内の4社から6神を合祀し、現在9神を祀っている。市指定の有形民俗文化財の若武者絵馬は、黒田藩四代藩・主綱政が、元禄14年(1701)に青木神社(祇園社)へ奉納したもので、筑前御用絵師の重鎮・狩野昌運の筆によるもの。元旦には獅子舞(市指定無形民俗文化財)が奉納される。

JR一貴山駅の東方500mほどの丘陵地にあり、全長103mの前方後円墳。
竪穴式石室で、古墳時代前期(4世紀後半)のものとみられる。
白銅鏡10面や刀剣、勾玉などが出土し、現在は京都大学総合博物館に保管されている。国指定史跡。

筑前国続風土記によると「桧原(ひばる)村の内にて橿原(かしわばら)の境にある禅寺なりしとかや今に其跡残れり。広さ78反ばかりあり、本尊観音は朽ちはて、仏体とも見えざる村人草の庵をかまえて入れ置きけり、那珂郡屋形原(現福岡市)に居たる千葉探題(たんだい)帰依の寺なりし故むかしは大寺なりしとかや」と見え、現在寺跡に阿弥陀如来坐像の石仏や梵字を刻んだ供養塔がある。

祭神は菅原道真。道真が袖の湊に上陸した際、漁人が舟の綱を輪にして敷物を作って出迎えたという伝説によるもので、江戸時代には綱輪天神と呼ばれていた。次第に綱場と呼ばれるようになり、現在も町名として残っている。

旧早良郡脇山村池田にある大日堂は、背振山東門寺の別院跡に、大村兵庫助、多々良興景という士によって天文年間(1532~1555)に建立された。貝原益軒の『筑前国続風土記』以来、近世の地誌類にも紹介されている。この堂に安置されている本尊の木造大日如来座像は、高さ130.5cm、檜材の寄木造りで、前面漆箔を施し、背面は漆仕上げで造られている。市指定の文化財。

元寇防塁のうち、長垂山から今山にかけての砂丘上には、豊前国が分担して防塁を築いた。現在は長垂海水浴場前と今山のふもとに国指定地がある。古文書には、築城郡吉富村を本拠とした成富氏が、乾元2(1303)年この地区の防塁の修理を完了したという報告があり、弘安の役(1281年)以後も防塁の修理が行われ、蒙古に対する警備体制が続いていたことを示している。

高祖山山麓の丘陵上にある前方後円墳。古墳の全長は64m、高さ6.5m、6世紀前半に造られたと考えられている。保存されている墳丘、同濠、外堤の規模は北部九州屈指。昭和52年に保存整備のため調査されたが、埋葬施設は未調査のため不明。

中国の歴史書「魏志倭人伝」に記された古代王国「伊都国」をメインテーマとし、市内の遺跡から出土した数多くの貴重な文化財や歴史資料を収蔵・展示している。中でも、世界最大の銅鏡「内行花文鏡」をはじめとする国宝「平原遺跡出土品」は必見。館内には、旧石器時代から現代まで学べる常設展示室や、広大な糸島平野を見渡せる展望スペース、文化財を分かりやすく紹介する映像スペースなどがある。
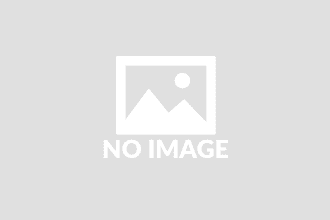
日本書記によると武内宿禰(たけうちすくね)の身替りとなって無実の罪に服して死んだ壱岐直真根子(いきのあたいまねこ)の忠魂を祭った社である。伝説では生の松原の地名は、神功皇后が松の枝を逆にさして戦勝を占ったとき、その枝が生きて栄えたことから付けられたとされている。後年その松は函松(はこまつ)といっていたが、今は枯れてしまってその一部を御神前に奉納され崇敬のまととなっている。

古第三紀志免層群名島層の砂山、礫岩層(れきがんそう)中に含まれる珪化木(けいかぼく)で、9個の円柱状石からなる。
香椎宮の社伝によれば、神功皇后が三韓出兵の時使用した船の帆柱が化石になったものとされている。
波打際の岩の上に輪切りにされた数個の丸い柱状の石が時をしのばせるように並んでいる。
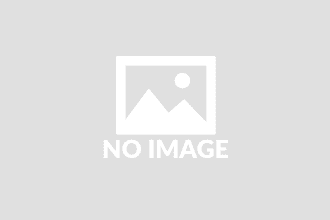
ここは、神功(じんぐう)皇后の新羅遠征で功績のあった武内宿彌(たけのうちのすくね)が、香椎在陣中に居住したと伝えられている。宿彌は300歳までも生きたという伝説の人である。
近くの不老水は宿彌の長寿にちなんだもので、以前は香椎宮の綾杉(あやすぎ)の木と共に皇室に献上されていた。不老水は長寿の神秘を物語るように、汲めどもつきぬ水を湧かせている。

大乗寺は法皇山宝珠院と号して、昔は奈良西大寺の末寺で律宗に属し、亀山上皇の勅願寺でありましたが、のち浄土宗に転じ、更に真言宗に改宗、大正9年(1920)長宮寺と合併して、中央区大手門一丁目に移り戦災で焼失しました。 この寺跡に亀山上皇が元寇の際、西大寺の叡尊(えいそん)に命じて、博多において敵国降伏の祈願を行わせた勅願石や、県指定文化財の地蔵菩薩板碑、蒙古碇石があります。


