愛しき歴史や文化を残しながら新たな博多へ
博多町家ふるさと館 館長・漫画家 長谷川法世さん
更新日:
.jpg)
歴史的なスポットや伝統文化体験など、福岡観光をさらに楽しむポイントを、地元の歴史や文化に精通する皆さんに教えていただく「地元の人に聞く!福岡の歴史・文化の魅力」インタビュー。今回は地元の歴史や文化をベースにした作品も多い博多出身の漫画家で、現在は「博多町家ふるさと館」館長も務める長谷川法世さんにお話をうかがいました。
取材対象者紹介
長谷川法世(はせがわほうせい)さん
福岡市博多区出身。福岡県立福岡高校卒業後上京し、1968年「正午に教会へ」で漫画家デビューした。のちに映画化された「博多っ子純情」など漫画を描きながら、小説、エッセイも執筆。TV・ラジオなどでも活躍している。2003年に「博多町家ふるさと館」館長就任。その後も「博多仁和加振興会」会長を務めるなど、今なお、博多の歴史や文化の継承に尽力している。
博多町家ふるさと館
所在地:福岡市博多区冷泉町6-10
TEL:092-281-7761
営業時間:10:00~18:00(最終入館17:30)
定休日:第4月曜(祝日の場合は翌平日)
入館料:200円(展示棟のみ。小・中学生無料)
https://hakatamachiya.com/
自然にストーリーが出てくるから漫画家に
先生が漫画家を志した経緯や理由をお聞かせください。
幼稚園の時「鉄腕アトム」を見てからです。ところが同じ高校で美術部だった3つ上の兄が「面白いからお前も入れ」と。特に興味があったわけではありませんが、兄が使っていた絵の具や筆も使えるし、すでに就職していた兄が「美術部に入ったら小遣いもやるし、絵の具代も出す」と言うので、最初は小遣い欲しさに。気付くと学業に影響が出るほど、夢中で絵を描くようになっていました。
その頃はもう漫画家志望ではなかったんですね。
授業中、わら半紙に万年筆で漫画を描いて、友だちにこっそり見せたりはしていました。「次はどうなるとや?」と楽しんでいる姿に「漫画もいいな」と思いましたが、当時は職業として認められにくいものでして。どうせなら芸術家として認められている絵描きを目指そうと思ったんです。
高校卒業後は上京しまして、画家のアトリエ兼研究所で学びながら、住み込みの新聞配達所で働きつつ美大進学を目指しました。しかし、絵を描いていると、ストーリーが出てくるんです。今スケッチしているこの家には、どんな家族が住んでいて、どんな日々を送っているとか。干している洗濯物から、こんな仕事をしているのかなとか。
絵を描いているのに、頭の中ではストーリーばかり考えているなんて、これは絵描きじゃない。やっぱり私は絵画より漫画のほうが好きだったんと気付きまして、それからは本格的に漫画家を目指すことにしました。
.jpg)
地元への想いから代表作「博多っ子純情」が誕生
先生の漫画は博多が舞台の作品が多いですが、やはり地元への想いがあるからでしょうか。
そうですね。私は「博多町家ふるさと館」のすぐ近くで生まれたのですが、小学生の頃から、家の都合で福岡市内を転々としていました。ただ、小学校は転校せず、中学校も博多へ通いました。今考えると、いずれ博多に戻りたいという父の想いもあって、そうしていたのかもしれないですね。
小学3年生から中学1年生までは「博多祇園山笠」にも出ていました。山笠を後ろから押していく「後押し」に付いて走るだけだったのですが、「中学2年生になったら山笠の舁き棒に付く!」というのを目標に。ところがその矢先に、家が糟屋郡に引っ越しまして、残念ながら私の博多人生がそこで終わりました………。
それが心残りということもあったのでしょうか。
そうですね。その時の悔しい想いが残っていたのかもしれませんが、漫画家になった時からずっと、博多弁で漫画を描いてみたいと思っていたんです。しかしその頃の東京では、福岡も博多もあまり知られていない存在。「誰も読まない」と却下されていました。
その後、漫画が売れ始めて、少し注目していただけるようになった頃、「漫画アクション」の副編集長から初めてオファーがきまして。逆に私にどんな漫画を描かせたいか聞いてみたところ、「これからは地方の時代ですから、あなたの国の話でも」と言われたんです。そこで「博多弁の漫画が描けるのなら」と、まずは単発で「博多っ子純情」を描きました。
それを評価していただいたことや、その後、博多の知名度が上がったこともありまして、すでに数年先までストーリーができていた「博多っ子純情」の続編をはじめ、博多を舞台にした漫画を描くようになりました。
「博多町家ふるさと館」館長就任で予想より早く博多へ
先生が「博多町家ふるさと館」館長に就任された経緯をうかがえますか?
読売新聞の連載「こりゃたまがった!」の原画展を、オープン間もない博多リバレインで開催していた時、新聞社の担当経由で声をかけていただきました。初代館長だった西島伊三雄先生が亡きあと約半年間、後任が決まっていなかったそうで、私にどうかとオファーしていただいたんです。
当時は関東に住んでいたので、「光栄なお話ですけど、頻繁には来れませんよ」と伝えたら、大きな催しがある時に出勤すれば大丈夫ということで、お引き受けしました。
いずれは博多に、との考えはありましたが、向こうにスタッフを何人も抱えていたので、すぐには難しかったんですね。その後数年かかりましたが、とはいえ、予想よりも早く博多に帰ってくることができ、福岡市民に復帰することができました。そのおかげで、福岡市民のみが受賞できる「福岡市文化賞」をいただくこともできました。
「博多町家ふるさと館」の館長おすすめポイントを教えてください。
歴史や伝統文化など、博多のことがコンパクトに予習できるところです。「博多祇園山笠」のビデオもずっと流れていますし、博多織や博多人形、博多張り子、博多独楽、博多曲げ物など伝統工芸の実演もやっていますので、館内をゆっくりご覧いただければと思います。また、観光ボランティアさんが常駐しているので、博多観光で分からないことがあれば、気軽に声をかけてください。
博多弁の漫画を描きたい!その一心で地元のことを猛勉強!
先生が博多の歴史や文化に関われるようになったり、特に意識されるようになったのはいつ頃からでしょうか。
博多の歴史や文化を意識するようになったのは「博多っ子純情」を描き始めてからです。日常的に暮らしていたのは幼い頃までですし、「博多祇園山笠」にも出なくなると、地元の大人たちと付き合うこともなくなりましたからね。知っていそうで、いざ漫画に描こうとするとよくわからないことも多い。博多弁の漫画を描くのなら、博多のことをもっと知らなければと、勉強を始めました。
もともと活字が苦手で、高校時代は「美大へ行くから受験勉強は必要ない!」と教科書もろくに読まなかったのですが、「源氏物語」を描くことになった時には、資料の単行本を6時間で一気に読んだことも。「今日描かないといけない!」と気合いが入ると、意外と読めるんです。高校の時しっかり受験勉強すれば、九州大学に行けたかもなんて思ってしまうくらい、文献なども読むようになりました。
ここの館長になってからはさらに勉強しようと、館長室にある博多の歴史や文化関連の本を読んだりしています。「博多っ子純情」の時に勉強が足りないと感じてからは、博多のことを勉強するのが積年の望みでしたから。最近はネットや電子辞書がありますから、昔に比べるとかなり調べものが楽にはなりましたね。
.jpg)
日本の動きに大きく関わってきた「文明のクロスロード」
ご地元のことを勉強された先生がお考えになる博多の歴史的・文化的な特徴や価値は何でしょうか?
昔から日本の玄関口で、文明のクロスロードだった博多は、日本の歴史や文化に大きく関わってきました。
広く知られているところでは、平安時代頃まで、大陸などからの国家使節を太宰府で接待する前に、防疫やおそらくスパイ対策も兼ねて逗留してもらった外交施設「鴻臚館」(こうろかん)。当時、すぐそばにある博多は、太宰府の「外港」の役割をしていたんですね。太宰府も京から役人が配置されるほど、当時の日本では重要な外交施設でした。
また、中国で入手した「灰吹法」を起用して、石見銀山で銀を大量に抽出できるよう本格的に開発したのは、豊臣秀吉と親交があった神屋宗湛(かみやそうたん)の曽祖父だったことや、江戸時代に志賀島で発見された国宝金印を、黒田藩に受け渡す仲立ちをした中に博多商人の才蔵がいたと言われているなど、歴史的・文化的な場面に、博多商人が登場することもあります。
ほかにも、唐と新羅から攻められた百済を助けるため、博多湾から170艘の船や27,000人もの援軍を送り、敗戦後は水城や大野城などが造られたという、660年の「白村江の戦い」(はくすきのえのたたかい、はくそんこうのたたかい)や、869年に博多湾に侵入した2艘の海賊船が、豊前の船から年貢用の絹綿を略奪された後に、選士を警護にあたらせるなど、博多や周辺の防衛強化につながった戦争や事件などもありました。
このように、調べれば調べるほど出てくる、日本の大きな動きにつながる博多のエピソードが出てくるのは、古くから日本の玄関口であり、文明のクロスロードだったからだと。これこそが、博多の歴史的・文化的な特徴だと思います。こうしたエピソードを知れば知るほど、私は博多のことをより愛おしく思えるんですよね。
博多の素顔が見える地祭もおすすめ
地元民の先生だからこそ知る、穴場的なスポットや博多をより楽しむポイントがあれば教えてください。
博多観光といったら大きな祭りもありますが、お盆を過ぎて8月下旬ごろまでに「千灯明(せんとうみょう)」という博多の地祭があります。町内ごとにお祭りの名前も少し違いますが、子どもたちがロウソクや、芯を付けた貝殻に油を入れて火を付けて、幻想的な雰囲気の中で祈りを捧げるという、いわゆる地元の人たちだけのお祭りです。
お堂がある所はお堂で、おこもりみたいに大人たちが飲んでいるんですが、そこで地元の人とお話ししたり、もしかしたら「あんたも飲んでいきなさい」ってお誘いがあるかもしれませんよ。「博多祇園山笠」の真剣で気合いを入れているからこその張り詰めた表情とは違って、地元民の素顔が見えると思いますので、博多を楽しみたいという方におすすめです。
受け継いだものに“ちょっといいこと”を加えて次の世代へ
先生が、これからの福岡市観光や文化発信に期待することはどのようなことですか?
いま、天神では都市開発が進められていますが、これからの博多は「開発」と「文化継承」を二律背反(にりつはいはん)で考えていかなければならないと思います。オフィスビルなども増えてきて、「博多祇園山笠」に出る人たちでさえも、実際にその流(ながれ)の地区が地元という人が少なくなっている。歴史ある祭りが継承されているから、何とか博多が博多として残っている状況だと思います。
受け継いだことを受け渡すだけでもかなりの労力が必要ですが、私たちは先人から受け継いだ歴史や文化に、ちょっといいことを付け加えることができれば幸いと思って、次の世代に受け渡していけばいいかと。その点、博多に「博多旧市街」と名前を付けてスポットを当てるなど、私はいい方向性で動いていると思いますので、これからも続けていただければ嬉しいですね。
.jpg)
最後に読者のみなさんへ、メッセージをお願いできますでしょうか。
現在の博多は豊臣秀吉の命による「太閤町割り」によって、通常10町四方(1町109m)に整備された、コンパクトな街ですから、行ってみたいと思うところにすぐに行くことができます。この中にはさまざまな歴史も詰まっていますから、見どころはたくさんありますしね。
また水炊き、うどん、ラーメン、もつ鍋など、博多ならではの食べもの屋さんもたくさんありますし、数は少なくなっていますが、昔ながらの喫茶店へ行けば、地元ならではの情報を得ることができますので、忙しくない時間帯を狙って、お店の人に話を聞いてみるのもおすすめです。「博多町家ふるさと館」でご案内している情報とともに参考にしていただいて、博多のいろいろな歴史や文化を楽しんでください。
インタビューで紹介したスポット
古き良き博多を体感できる「博多町家ふるさと館」
展示棟と町家棟、2つの棟で、博多の歴史や文化、伝統工芸品など、展示や実演など、古き良き博多を体感できる施設です。また、開放された休憩スペースもあるので、旅のひと休みにもおすすめです。また、伝統工芸品の制作体験なども行われているので、ホームページでチェックを。



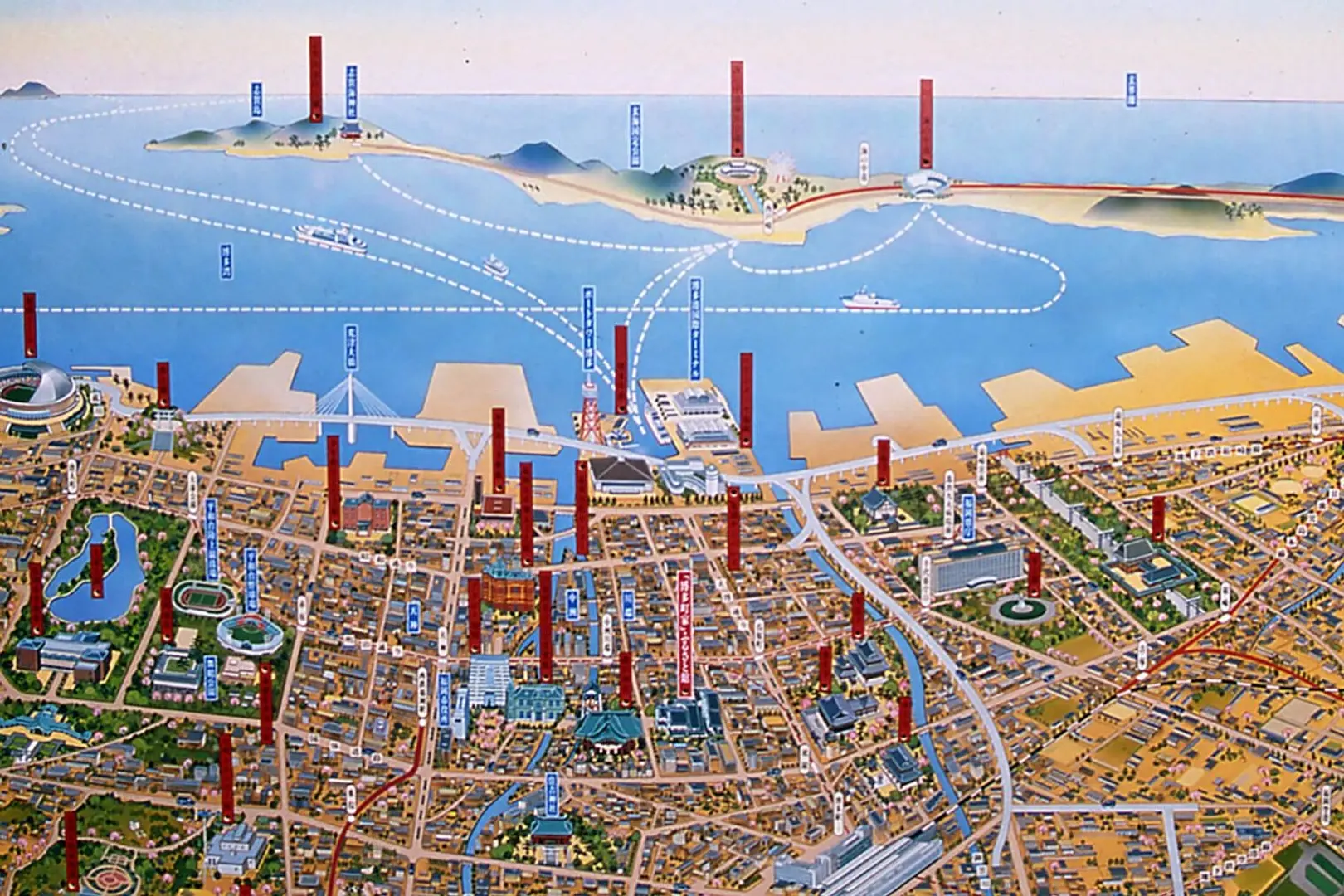
.jpg)
